2025年11月3日(月)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:マドモアゼル愛
こんにちは、悟(さとる)です。
本日はテレフォン人生相談から、夫を亡くした67歳の女性が、同居する42歳の長男の「人が嫌い」「人付き合いをしたくない」という態度に悩み、さらに自分自身の気持ちも「変わりたい」と揺れておられるご相談です。
ではこのお話を丁寧にたどって行きましょう。
相談者の背景と心にある不安
今回のご相談者は67歳の女性。
4年前にご主人を亡くされ、現在は42歳の長男と二人暮らしです。
外で働く長男が経済的にも生活面でも支えになっており、休日には一緒に食事に出かけるなど、表面上の関係は決して悪くありません。

しかしこの一年ほど、長男が突然「人が嫌い」「もう人付き合いはしたくない」と話すようになり、母親として強い不安を抱くようになりました。
「このまま息子は孤立してしまうのではないか」
「わたしが先にいなくなった後、息子はひとりになってしまうのではないか」
そんな思いが日々募っていったのです。
一方でご相談者ご自身も、「今の自分を変えたい」「もっと積極的に生きたい」「気持ちの持ち方を変えなければ」という思いが強くなっています。
息子の将来を案じながら、自身の残りの人生についても深く考えるようになっているのです。
長男が語る“人が嫌い”という言葉の背景
相談者の話から見えてくるのは、長男がとても気遣いの多い性格であること。
これまでの人生で、何度も人間関係に疲れを感じたり、うまく関係を築けない経験をしてきた可能性があります。
その結果、「もう人と関わりたくない」「必要以上に人に気を使うのがしんどい」という結論に至ったのかもしれません。
マドモアゼル愛氏は、この「人が嫌い」という言葉を字面通りに受け取らないよう助言されました。
人が嫌いになったのではなく、
- 人に合わせ続けて疲れた
- 無理に人間関係を維持しようとしなくなった
- 選ぶ人間関係だけ続けたい
そうした心理があるのではないかというのです。
実際、母親とは良好な関係を維持し、週末には外食にも出かけています。
つまり、長男は「すべての人間関係を放棄している」のではなく「安心できる関係だけ残している」ということなのです。
専門家が指摘した“親子の役割の逆転”
愛氏が着目したのは、相談者が気づいていない“親子関係の構造”でした。
長男は42歳。
一般的には、母親を気遣い、自立しながら関係を適度に保つ年代です。

しかし相談者は、息子の人生を大きく案じ、「わたしがいなくなったら息子はどう生きるのだろう」と心配している状態です。
愛氏はここに「役割の逆転」を見ています。
本来、息子が母親を気にかけるべき年齢であるにもかかわらず、相談者は「息子の将来が心配で眠れない」ほどに思い詰めている。
実際には、休日に母親を誘ってくれる息子の姿から見えてくるのは、息子のほうが母親を気遣っている構造です。
相談者が「息子を背負う」立場から、「息子に気遣われている自分」を受け入れることが、ふたりの関係を自然に整える鍵になると愛氏は示しました。
“息子を変える”のではなく “自分が変わる”ことの大切さ
相談者は「このままではいけない」「気持ちを変えたい」とご自身の内面にも変化を望んでいます。
愛氏はこの点に着目し、「変化の主体はまずあなた自身です」と語りました。
息子を変えようとするよりも、相談者自身が人とのつながりを持ち、自分の生活を豊かにするために動くことが大切だというのです。
例えば、
- 趣味を見つける
- 地域の集まりに参加してみる
- 新しい友人関係を築く
- 家族以外の人とのやりとりを増やす
こうした“外の世界との接点”を増やしていくことが、自身の充実感につながり、結果的に息子とも良い距離感を作るきっかけになる可能性があります。
将来の不安に囚われすぎず、“今を生きる”こと
相談者は「自分がいなくなったときの息子」の姿を強く想像して不安に陥っていました。
しかし愛氏は、将来の心配に囚われるあまり、いま目の前の生活や感情をおろそかにしてしまう危険性を指摘しました。
特に67歳という年齢を踏まえると、「これからの人生をどう生きたいか」「今日をどう過ごしたいか」を大切にすることが心の安定につながります。
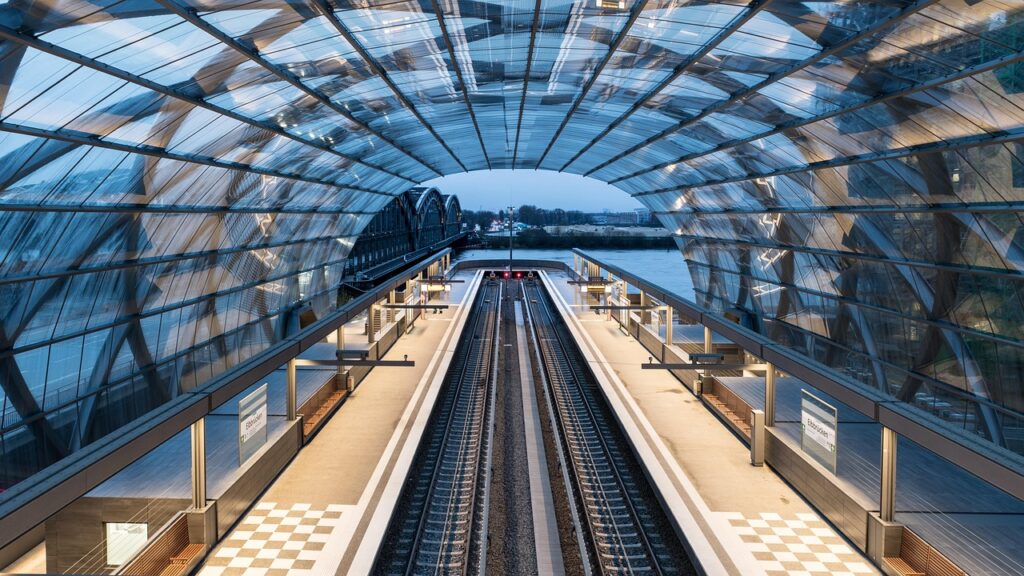
未来の不安は尽きませんが、不確実な“これから”より、今まさに生きている“今日”に視点を戻すことで、心の重荷は少しずつ軽くなっていきます。
相談内容から見える本質とは
今回の相談には、「親子の距離感」「自立」「人間関係の疲弊」「老後への不安」といった普遍的なテーマが含まれています。
長男の言葉を単なる“拒絶”ではなく、「自分を守るための選択」「関わる相手を絞る生き方」として見る視点は、多くの人間関係にも応用できます。
また、相談者が抱える葛藤は「母親としての自分」と「一人の人間としての自分」の狭間で揺れる姿でもあり、中高年の多くの方にとって他人事ではないテーマでしょう。

愛氏の助言から浮かび上がる本質は、「自分の人生を主体的に生きることが、周囲との関係も変えていく」という普遍的な真理でもあります。
まとめ
本日は、同居する42歳の長男の“人付き合いをしない”姿に不安を抱く67歳の母親のご相談を、テレフォン人生相談からご紹介いたしました。
息子を深く思う気持ちと、自分自身の人生への問い直し。
その二つが重なりながら揺れるご相談者に対し、専門家からは「親子の役割」「言葉の裏側にある心理」「自身が変わることの大切さ」「今を生きる視点」が示されました。
人生には正解がありません。
しかし、誰かの悩みを知ることで、自分自身の視野が広がったり、心が少し軽くなる瞬間があるものです。
放送はこちらから視聴できます
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
このブログが、読んでくださった方の「明日を生きるヒント」になれば幸いです。
またぜひ遊びに来てくださいね。
以上、悟(さとる)でした。
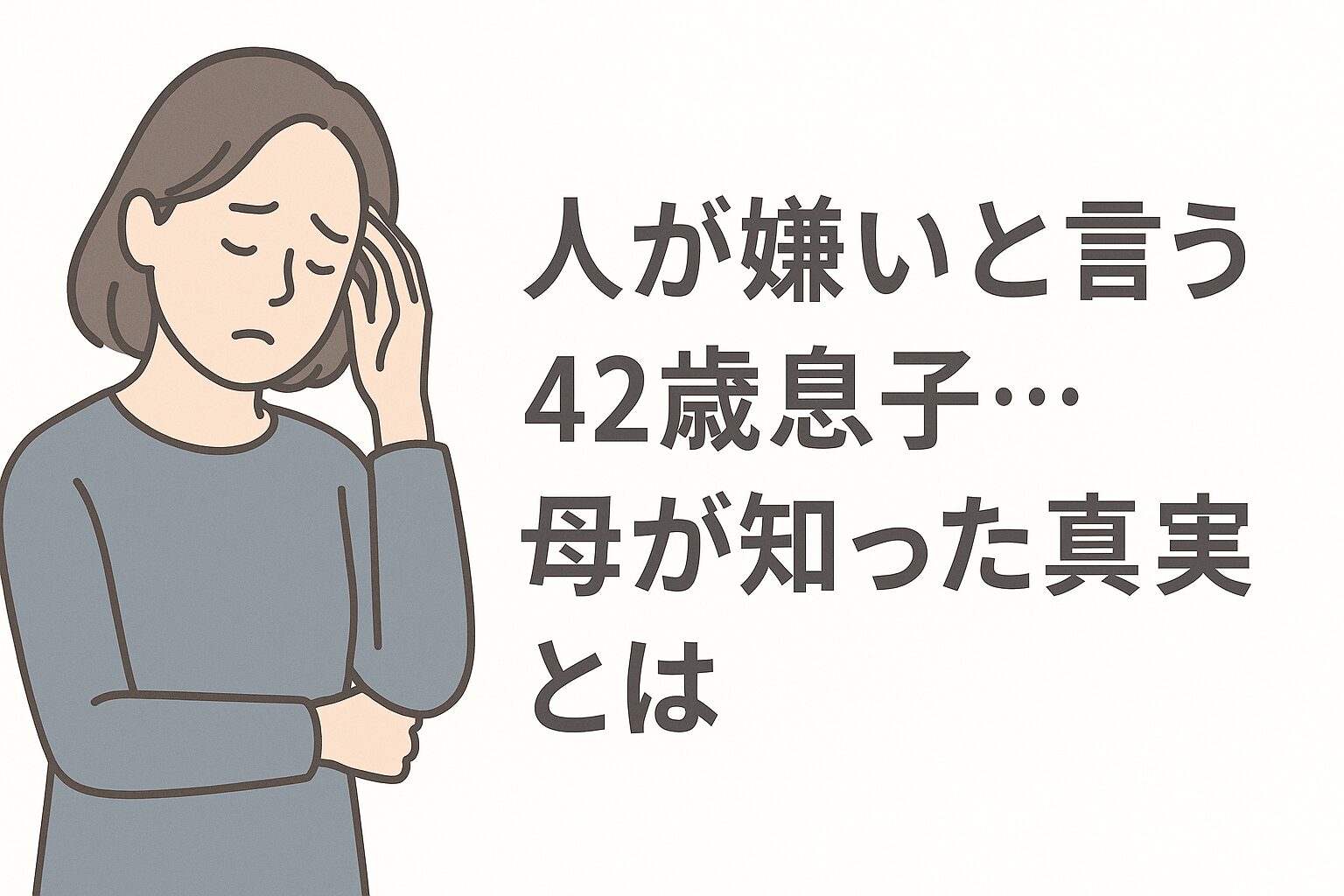
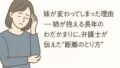

コメント