
こんにちは、悟(さとる)です。
きょうは、夫婦の暴力、不倫の後悔、会話の行き違い、相続やお金の不安、そして子どもの結婚をめぐる迷いまで、寄せられたさまざまな相談内容を私なりに整理しました。
専門家の先生方の言葉をたどりながら、事実関係とアドバイスを丁寧にまとめたつもりです。
どうぞ気楽にお読みください。
今回扱うテーマの全体像
夫婦・家族にまつわる相談は、表面上は別々に見えても、奥底では「安全」「信頼」「境界」「選択」という共通の軸に触れています。
番組では、各ケースの具体的状況を確認したうえで、カウンセラー・精神科医・弁護士・メンタルトレーナーらが、それぞれの立場から助言を行いました。
本記事では、ケースごとに事実経過と助言の要点を整理し、「いま何が起きているか」「どう捉えると道が見えやすいか」を段階的にまとめます。
夫のDVに悩む47歳の相談者
相談の要点
結婚4年目。1年目以降、年に1回程度の蹴りがあり、直近では頭部への拳打や威嚇的な動作が複数回続いたとのこと。
負傷は青あざが数週間残る程度で、急所は避けられているという自己観察も語られました。

親きょうだいに相談するも、「夫は良い人だから別れない方がよい」と諭され、孤立感が募っています。
夜の関係はほぼなく、会話も乏しい状況です。
専門家の主な助言
番組では、まず「暴力は異常であり、認めてはならない行為」と位置づけたうえで、相談者自身の「一人で生きる力」の問題に着目し、「別れの決断を妨げる要因」を心の面から指摘しました。
また、加害行為の抑止に向けた具体的伝え方(健康被害の具体的説明など)や、夫婦のスキンシップ・コミュニケーション全般の見直しにも言及がありました。
このケースには、①暴力という安全の問題、②家族・親族の反応による二次的な孤立、③性生活・会話の断絶、という三層が重なっています。
ここでは「安全確保の優先」「心の自立」という二つの観点から、現状を見直す示唆が提示されました。
37年前と15年前の夫の不倫が忘れられない66歳の相談者
相談の要点
夫の不倫は長期に及んだ時期があり、現在は同居し、日々は穏やかに過ごしているものの、当時の記憶が繰り返し浮かび、心療内科に通院中。
夫は価値観として不貞を重く捉えていないのでは、という見立ても語られました。
専門家の主な助言
精神科医は、過去の出来事が現在の生活に影を落としている構図を説明し、「いま、ここにいる二人」を大切にする姿勢や会話の再構築を提案しました。

価値観の相違(不貞を裏切りと捉える/捉えない)を前提に、受け止め方の選択が長い生活の質を左右する点が強調されました。
①過去と現在の切り分け、②価値観の不一致の扱い方、③日常の共同作業(運動・外出など)の再設計という三点が、長期の同居生活の安定に関わる軸として示されました。
夫の不倫疑惑と3人の幼い子を抱える33歳の相談者
相談の要点
夫の趣味(撮影)を通じた独身女性との親密化、近所の既婚女性との接触など、複数の疑いが重なり、家庭内の信頼が崩れました。
夫は否認を続け、幼い男児3人の養育が続く中で、離婚すべきか逡巡しています。
専門家の主な助言
評論家は、現時点での離婚選択の不利益(育児負担・父性の関与欠如による影響など)を指摘。
夫が否認する背景(認めれば関係が壊れる・家族を傷つける)にも触れ、事実確定に固執するより、現に必要な育児機能を家庭内に戻すことの重要性が語られました。

そして具体策として、夫に家庭内で果たしてほしい行動(子の世話や家事)の要望を明確に伝えるアプローチも提案されました。
①事実認定の困難に伴う停滞を避けるための行動指針、②子どもの利益を中心においた役割分担の再編、③「非難」よりも「要望」の言語化が、再建の第一歩として整理されました。
80歳・配偶者を亡くした後の相続とお金の不安
相談の要点
夫死亡後、預金と自宅を相続。自身の手持ち資産や過去の保険・年金商品の取扱い、税務手続きの未申告の可否、遺族年金の収入要件との関係など、複数の不安が重なりました。
誰に相談すべきか、情報漏えいの不安も語られました。
専門家(弁護士)の主な助言
税務や金融商品の扱いは種類により異なるため、一般論の混同を避け、正確な属性確認(控除対象かどうか、源泉課税の有無等)を行うことが必要とされました。
確定申告の「控除を申請しなかったこと」自体は直ちに非とされるものではなく、現状からの適切な整理と今後の手続の整備が重要と説明。
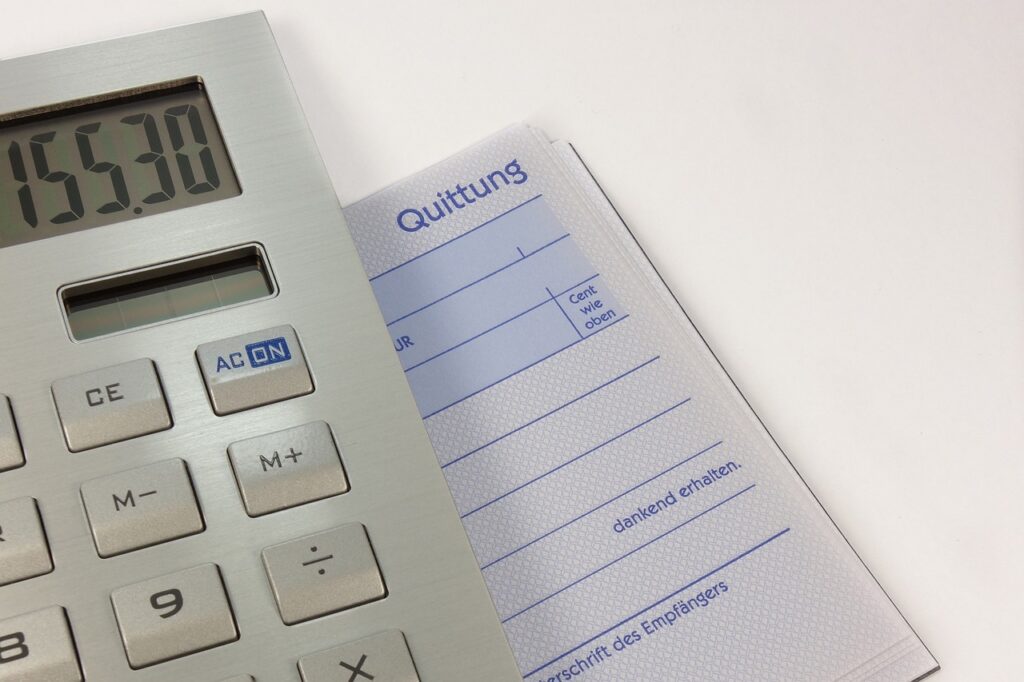
秘密保持義務を持つ専門家(税理士、信頼できる金融機関、FP)や、家族(息子)の関与のもとで、安全に相談ルートを作ることが推奨されました。
①商品ごとの税務区分を分けて理解する、②「誰に、何を、どこまで」開示するかの安全設計、③息子など信頼できる家族と専門家を橋渡しにして、曖昧な不安を具体的課題へ置き換える——この三手順が提示されました。
会話がなくなった夫婦(妻51・夫53)
相談の要点
娘の独立を機に、会話・共同の食事・外出が消え、妻の側に「嫌悪」感が蓄積。
夫は暴力や浪費などの問題はなく、周囲からは「我慢を」と言われるが、今後を決めきれずにいます。
専門家の主な助言
メンタルトレーナーは、「楽しい」の基準が人ごとに違う前提に立ち、相手の内面に目を向ける態度の再学習を促しました。
また、自身の「嫌い」の正体を言語化する作業(何が・どの程度・なぜ)を提案。

これにより、相手に求めることと自分で調整できることの境界が見えやすくなる、と示されました。
①評価語(嫌い・つまらない)の具体化、②相手の楽しさの源泉の再確認、③そのうえでの同居設計の現実的な再交渉、という段取りが見取り図として提示されました。
既婚の自身が不倫発覚し、夫が弁護士対応を希望(妻44)
相談の要点
二度の不倫歴のうち、現在進行の相手とのやり取りが夫に露見。
夫は弁護士を介した「けじめ」を希望する一方、不倫相手は家庭や職場への波及を恐れ、弁護士回避を求めています。
相談者は夫婦再構築を望みつつ、処理手続の選択で板挟みに。
専門家(弁護士)の主な助言
夫本人が直接相手に働きかけるより、弁護士を介した方が手続の安全性が高い点が説明されました。
相手側の家庭・職場に通知が届くリスクを減らすには、相手が自発的に弁護士へ連絡を取り、連絡手段を確保する方法があること、また、慰謝料支払と求償の循環(共同不法行為における負担関係)を避けるためにも、適式な和解・合意書の作成が望ましいとされました。

①感情の対立と手続の安全確保は分けて進める、②当事者間だけで閉じず、法的な交通整理を行う、③連絡経路を事前に整え、波及リスクを抑えるといった段取りが示されました。
次女29の婚約相手42と「肌のふれあいがない」——母60の迷い
相談の要点
交際・同居を経て1年。
身体的親密さがなく、娘はつらさを訴えるものの、決断は揺らぎ、母が仲介すべきか逡巡しています。
7-2 専門家の主な助言
メンタルトレーナーは、母が「解決を決めない」姿勢を守り、複数案の提示(選択肢の可視化)とメリット・デメリットの整理を助ける役割を提案。
進路の最終決定権は娘本人にあることを明確にし、意思決定の練習を支える関わりが示されました。
司会からは、母自身が娘の問題へ過度に関心を向ける背景(自身の不満)を自覚し、まず自分を整える必要性にも触れられました。

①第三者(親)が解決を「決めない」、②選択の棚卸しを手伝い、本人の意思決定力を支える、③親自身の生活の充実を並行して整える——この三点が示唆されました。
結婚1年半・多忙な夫と「話せない」40歳——回避依存への言及
相談の要点
入籍後、夫婦の会話が極端に減少。
目を合わせない・スマホ回避などの行動が続き、相談者自身も人付き合いが得意ではない自覚があります。
専門家の主な助言
弁護士は、成人後の人格傾向は大きく変わりにくいため、相手を変える前提ではなく「その相手と自分が続けられるか」を判断基準に据える現実的視点を提示。
司会からは、人と親密になることを避けてしまう傾向(回避依存)という概念が紹介され、自己理解の手がかりとして言語化が促されました。

①「相手を変える」前提から「自分は続けられるか」への軸足移動、②行動特徴(目を合わせない・回避)をラベルで理解し、対処の起点にする、③そのうえで生活設計を選ぶ——という見通しが示されました。
専門家の言葉から見えてくる共通の軸
安全の最優先
身体的暴力が関わる局面では、まず安全の確保が不可欠と位置づけられました。
恐怖や負傷が継続する場合、環境を変える・支援窓口につながるなど、具体的手立てが前提となります。
価値観の不一致と時間軸
不倫のように価値観が割れる事柄では、「過去」と「現在」を分けて扱う視点が繰り返し示されました。
現在の生活をどう維持・改善するか、そのために何を受け入れ、何を線引きするか。

時間軸の整理が、感情のループを緩める鍵として扱われています。
役割と言語化
育児や家事の役割が滞っている時は、非難より要望、抽象語より具体行動の提示が有効とされました。
何を、いつ、どの程度、どうしてほしいのか。言語化は交渉の土台になります。
手続の安全設計
不倫の事後処理や相続・税務など、法的・実務的な整理は、適式な窓口と手順に乗せることで、感情の対立や情報漏えいのリスクを抑えられます。
専門領域の線引きと関与の順番が、安心につながります。
自己理解と境界線
回避傾向や「嫌い」の正体を言葉にし、相手と自分の境界を引く。
親子場面でも、解決を「決めない」支え方が繰り返し提案されました。

自分の課題と他者の課題を分けることが、選択を軽くします。
まとめ
痛みや迷いは、それぞれの場面で形が違います。
ただ、どのケースにも「安全」「言葉」「手続」「境界」という共通の鍵がそっと置かれていました。
鍵の置き場所が分かると、扉の前に立ち尽くす時間が、少しだけ短くなります。

必要なときに専門家を頼り、家族や信頼できる人と事実を整理しながら、今日の自分が選べる一歩を丁寧に選んでいけますように。
放送はこちらから視聴できます➡【テレフォン人生相談】 2025年10月18日
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
人生に正解はありませんが、誰かの悩みを知ることで、自分の心が少し楽になったり、新しい考え方に気づけることもあります。
このブログが、読んでくださった方の「明日を生きるヒント」になれば嬉しいです。
またぜひ遊びに来てくださいね。
以上、悟(さとる)でした。
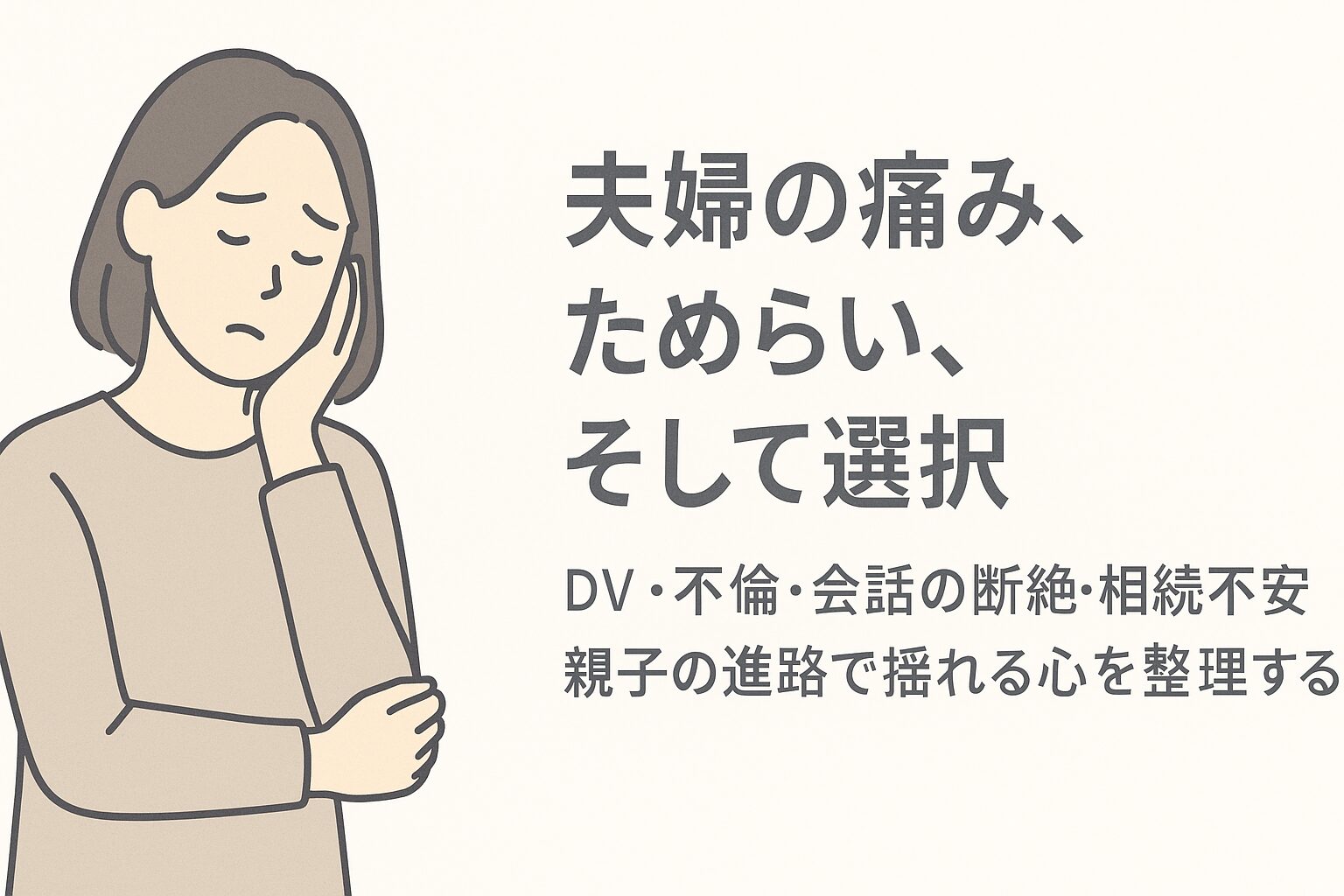
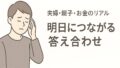
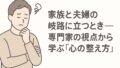
コメント