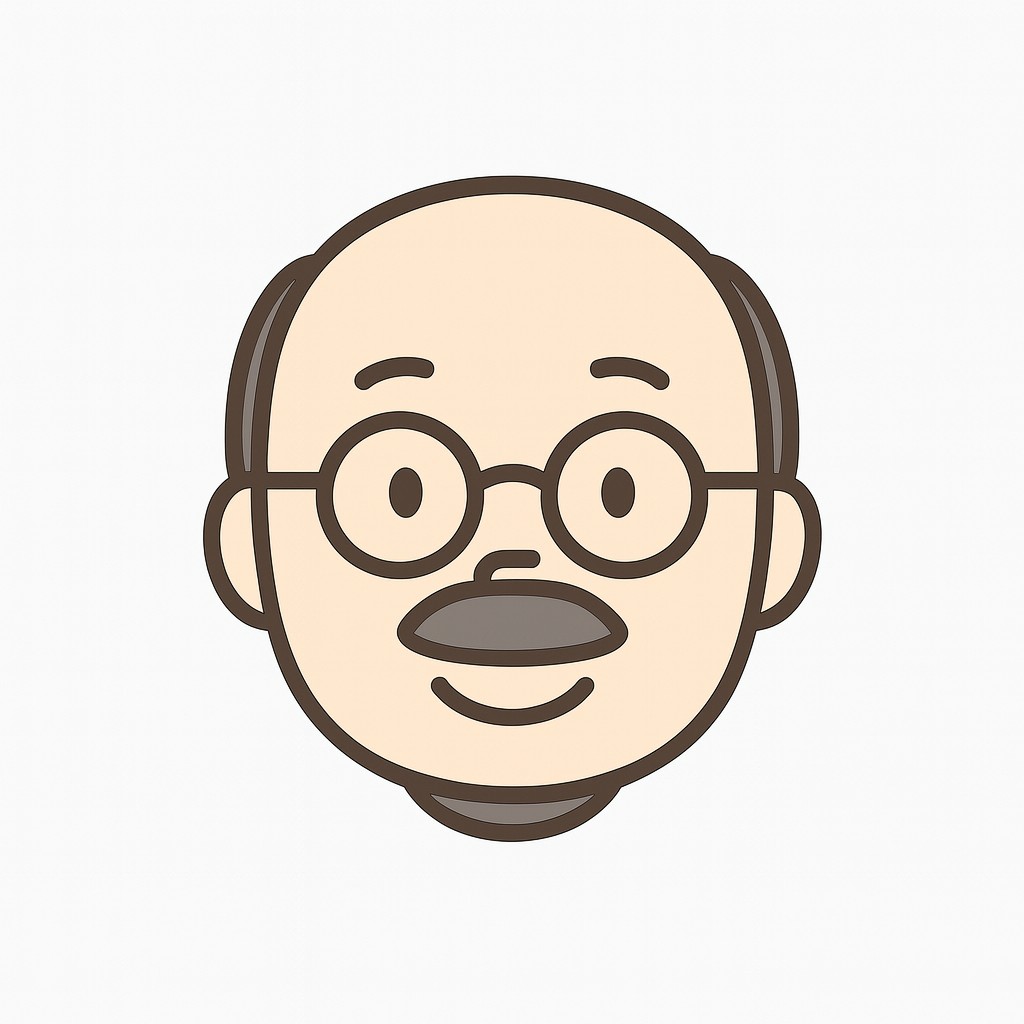
こんにちは、ふくです。
日々の暮らしのなかで、気づけば頭の中が悩みでいっぱいになってしまうことはありませんか。
そんな時、無理に気合で乗り切ろうとすると、心はますます重くなるものです。
今回は、岡田斗司夫先生が語られた「悩みの扱い方」を、わたしが道案内役として静かに整理してお届けします。
難しい専門用語は使いません。
今の自分に必要なところから、ゆっくり読み進めてみてくださいね。
悩みは「頭の作業台」を圧迫する——まずは外に出す
人は悩み始めると、頭の中の“作業台”に問題を積み上げ続けてしまいます。
作業台に載る重さには限りがあり、載せ過ぎると動けなくなる。
岡田先生は、この状態を軽くするための第一歩として「書き出す」ことを勧めます。
頭の中で“もくもく”と回り続ける心配や不安を紙に移すと、記憶の保持を紙に委ねられます。
すると、「覚えておかなければ」という負担が外れ、考えるための余力が戻ってきます。
ここではまだ何も解決していません。
それでも、悩みが“見える化”されるだけで、心の圧迫感は和らぎ、具体的な検討へと進める呼吸が生まれます。
書き出したら「仕分け」へ——“今に関係すること”を中央へ
書き出しの次は「仕分け」です。

岡田先生は、目の前の紙を“作業台”に見立て、今すぐ扱うべきものだけを真ん中に置き、他は外にどけます。
ポイントは「今の自分に関係があるか」。
過去の出来事や将来の漠然とした不安は、どれほど重大に感じられても“今ここ”の意思決定には直接関係しない場合が多いものです。
作業台の中央に残すのは、期限や行動が伴う「手を動かせる問題」。
その一点に絞ることで、思考の焦点が定まり、行動の順番も見えてきます。
具体例:シングルマザーの相談を“今だけ”に絞る
岡田先生が取り上げた相談に、次のようなものがありました。
——27歳のシングルマザー。過去の生育歴や辛い経験、現状の不安が長く綴られる一方、最後に「マンションのローンが払えず、あと3か月で退去」という切迫した一文が置かれている。
先生はここで、相談内容を「今に関係すること」と「今は関係しないこと」に色分けすると良いと示します。
すると、このケースの“今”は「退去までの3か月をどう切り抜けるか」に尽きると分かる。
役所の福祉窓口、母子支援制度、住まいの緊急相談、収入確保の現実的導線。
まずはそこだけを考える。
過去の痛みや将来の教育不安は大切なテーマですが、いったん作業台の外へ置く。
こうして“一点集中”に切り替えることで、心の余白が戻り、具体的な行動が打てるようになります。
「わかっているのに動けない」を越える——計画は“できた気”を生み、余力を返してくれる
夏休みの計画表を作ると「やれそうな気がする」あの感覚。
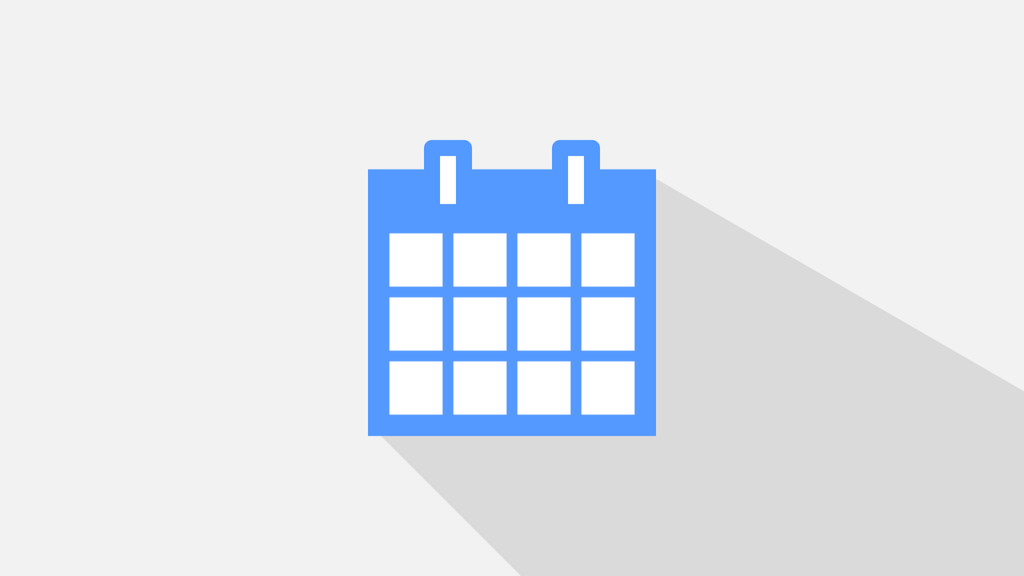
岡田先生は、これを悩みの運転にも応用します。書き出し・仕分けを経ると、未完成でも“行けそう感”が心に宿り、緊張で固まった思考がほどけます。
重要なのは、解決が先ではなく、整えるのが先だという視点です。
整えば、はじめて問題に手が届きます。
解決だけが正義ではない——悩みに対する5つのアプローチ
悩みを前にしたとき、人はつい「解決」一択で考えます。けれど、先生は選択肢を五つに広げます。
- 解決する
- 逃げる
- 保存する
- 忘れる
- 共有する
このうち「1」以外は、厳密には“解決”していません。
しかし日常の悩みの多くは、時間の流れや状況の変化のなかで**“どうでもよくなる”**か、自然に収束することが少なくない。
「逃げる」は、あえて手を出さず問題から距離を置く選択。
「保存する」は、ノートや記録に置いて忘れない工夫をしながら、今は扱わないと決めること。
「忘れる」は、意図的に意識の外へ送る技法。「共有する」は、人に話して負荷を分散すること。
どれも心の負担を下げ、行動できる状態を回復させる働きがあります。
そして、共有は特に即効性が高い手段として語られます。
言語化し、他者に届く形に整えること自体が、仕分けの深化になるからです。
視点を変えるだけで軽くなる——“面白がる”という客観視
先生は、重たい出来事に直面したときでも「客観視」することで心の重さが軽くなると話します。
それをあえて「面白がる」と表現します。

自分を少し上空から眺め、物語の登場人物のように捉える。現実は変わらなくても、主観の軸がずれるだけで、圧迫感は和らぎます。
これは“無責任”になることではありません。
主観に押しつぶされない立ち位置をつくる、心の安全帯のようなものです。
具体例:スマホを見てしまった恋の悩みを「証拠」と「気持ち」の二軸で捉え直す
別の相談では、交際相手のスマホを見てしまい、浮気を示す文面を知った女性の苦悩が語られました。
相手は逆に「プライバシーの意識が低い」と説教をしたという話です。
ここで先生は、相談文の“本音”を読み解きます。女性は「謝るべきか、騙されているのか」と尋ねていますが、実際には既に別れている。
つまり、彼に謝る必要の有無は本質ではない。
本当の問いは「自分はどう向き合いたいか」。

そこで先生は判断の軸を二つに整理します。
証拠ベースで判断するなら、事実を集め、整合性から決める。
気持ちベースで判断するなら、「もう信じられない」という自分の心の声を根拠に決める。
どちらが正しいか、唯一の答えはない。どちらの自分が好きかで選んでよい。
この捉え直しは、悩みを抽象的な罪悪感や後悔から切り離し、意思決定の軸を手に戻してくれます。
「整理 → 仕分け → 並べ替え」で、行動へ落とす
先生はさらに、仕分けを終えた後の「並べ替え」の効用も示します。
旅行計画を時系列に並べると、移動と食事と宿泊の像が立ち上がるように、悩みも期日や優先度で並べ直すと、自然に“次の一手”が現れます。
作業台の中央には「今すぐ扱う一件」だけ。
周囲に「近い将来の検討事項」を置き、遠くに「いつか考えるテーマ」。
これだけで、無力感は大きく後退します。
感情の洪水とどう付き合うか——「言語化」が呼吸を取り戻す
悩みの渦中では、私たちは言葉にならない感情に飲み込まれがちです。
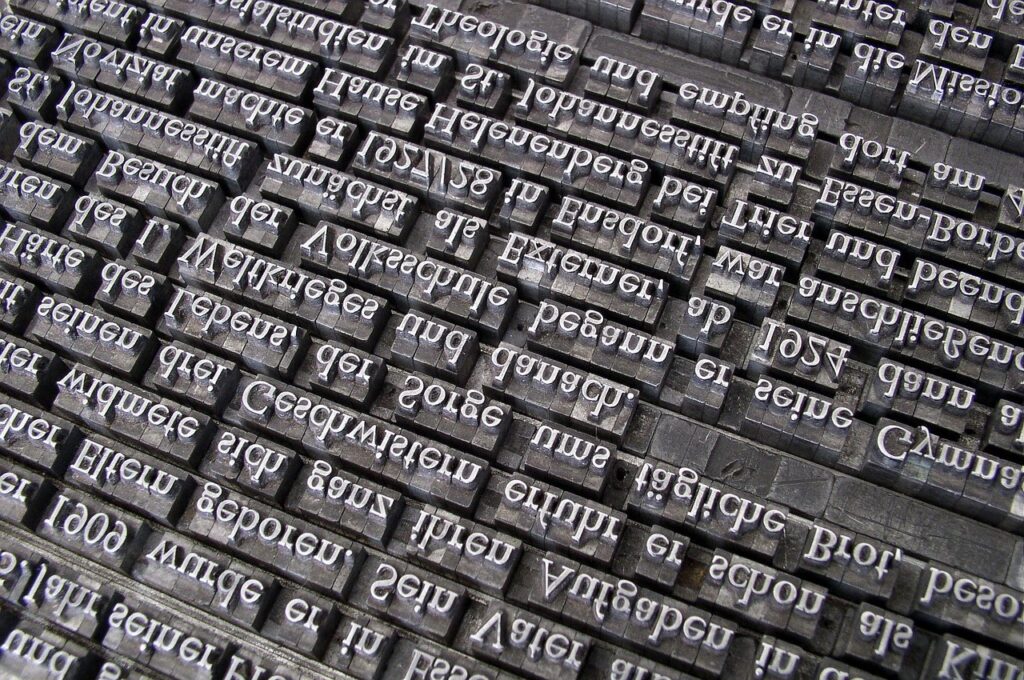
先生は、言語化こそが感情の水位を下げる装置だと指摘します。
書く・話す・声に出す。
どの形でも構わないから、言葉にすることで、感情の輪郭が整い、扱い方が見えてきます。
言語化の一回目は荒くて大丈夫。
二回目、三回目と重ねるうちに、不用な情報と核の情報が自然に分かれていきます。
「人に話せない」人のための道具——紙とペンが味方になる
誰かに話すのが難しい人もいます。
そんなとき、紙とペンは身近で頼れる相棒です。
箇条書きでも、手書きの落書きでも、音声メモでもかまいません。
岡田先生は、書くことそのものに**カタルシス(浄化)**があると語ります。
紙が“覚えてくれる”から、人はやっと手放せる。
手放したスペースに、行動や判断の力が戻ってきます。
過去と未来の“重石”を外す——「今」に集中する
過去の傷や将来の不安は、確かに大切なテーマです。
ただ、作業台の中央を占拠させてしまうと、足が止まります。
岡田先生は、「今」に直接関係することに集中するよう繰り返し促します。

シングルマザーの例でいえば、3か月後の住まいが“今”です。
家計・制度・支援・交渉。ここだけに光を当てる。
過去の痛みのケアや将来の設計は、“今”を越えた後に、あらためて落ち着いた環境で向き合う方が、かえって良い結果につながります。
それでも「解決」にこだわりたくなる心へ——選べる道を増やす
私たちが解決に執着してしまうのは、「そうしなければ前へ進めない」と思い込むからです。
けれど、先生はあえて選択肢を広げます。
逃げてもいい、保存してもいい、忘れてもいい、共有していい。こうして**“選べる”状態**に戻ることが、実は最短距離での前進になります。
心が固まってしまうと、唯一の正解にしがみついて身動きがとれません。
選択肢を増やすことは、心の可動域を取り戻すことです。
まとめ——悩みを小さく、行動をやさしく
岡田斗司夫先生の話から浮かび上がるのは、「解決できないときの、上手な持ち方」です。
まず、紙に書いて外へ出す。

次に、今に関係する一点だけを作業台の中央へ。
必要に応じて、解決・逃げる・保存・忘れる・共有を使い分ける。
しんどさが増したら、客観視で“面白がる”位置へ少しずれる。
そして、時系列や優先度に並べ替え、行動の一歩を具体に落とす。
これらはどれも、心を荒立てずに前に進むための、静かな手順です。
動画視聴はこちらから↓
賢い人がやっている思考法【悩みのるつぼ/サイコパス人生相談/悩み95%解決/岡田斗司夫/切り抜き】
最後まで読んでくださって、ありがとうございます。
悩みは、無理に一気に片づけなくても大丈夫です。
まずは紙に書き出して、今必要な一つだけをそっと手元に残す。
その繰り返しで、心はちゃんと軽くなっていきます。
今日からできる小さな手順が、きっとあなたの明日に呼吸を返してくれます。
どうか安心してくださいね。
今日も心がふっと軽くなりますように。
以上、ふくでしたー
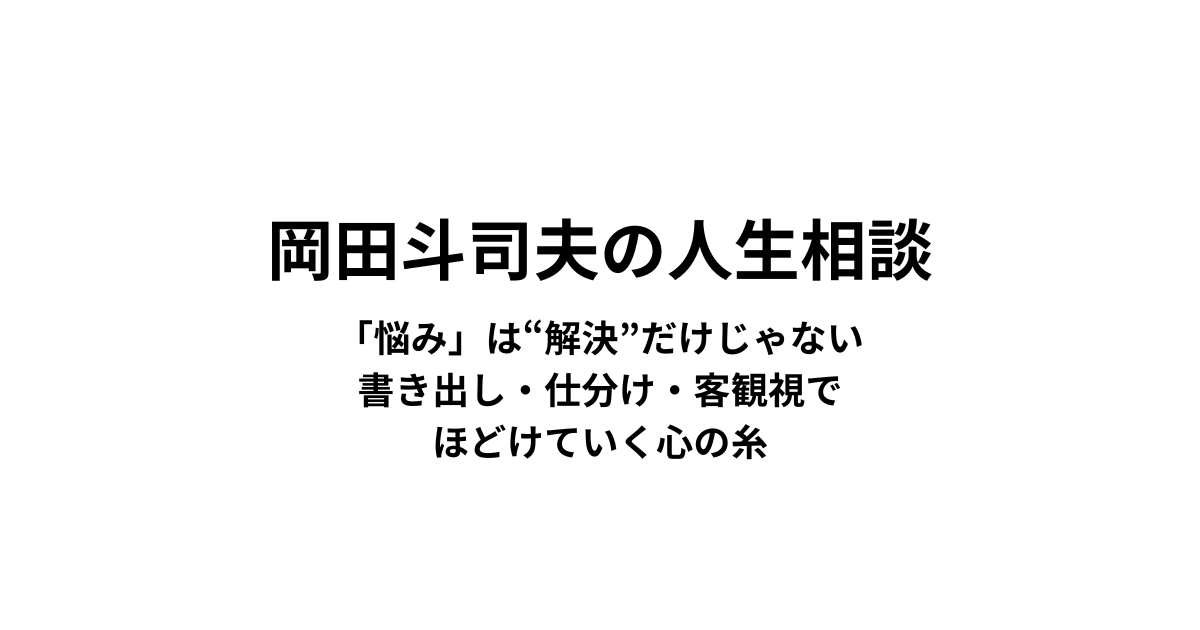
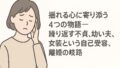

コメント